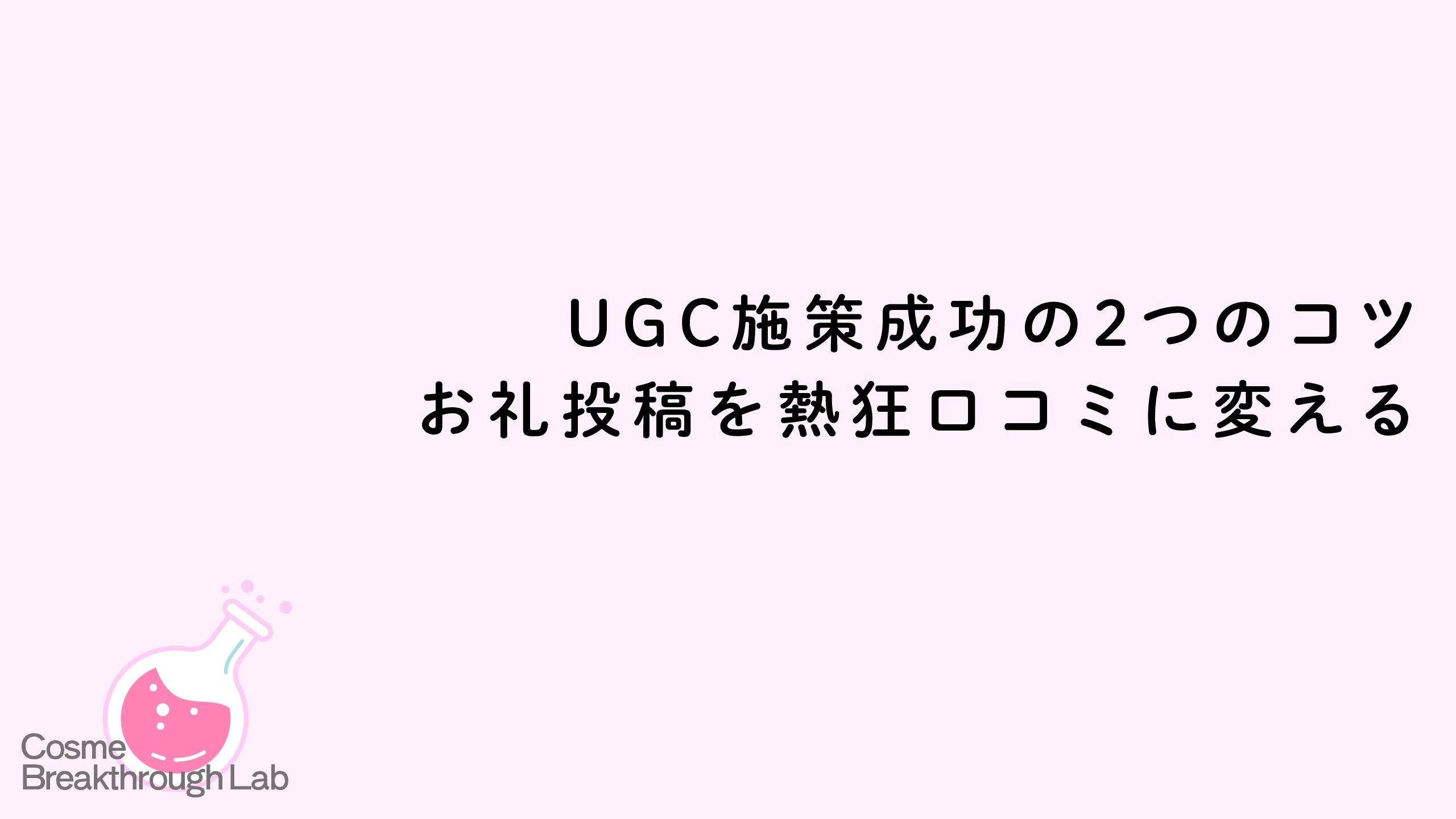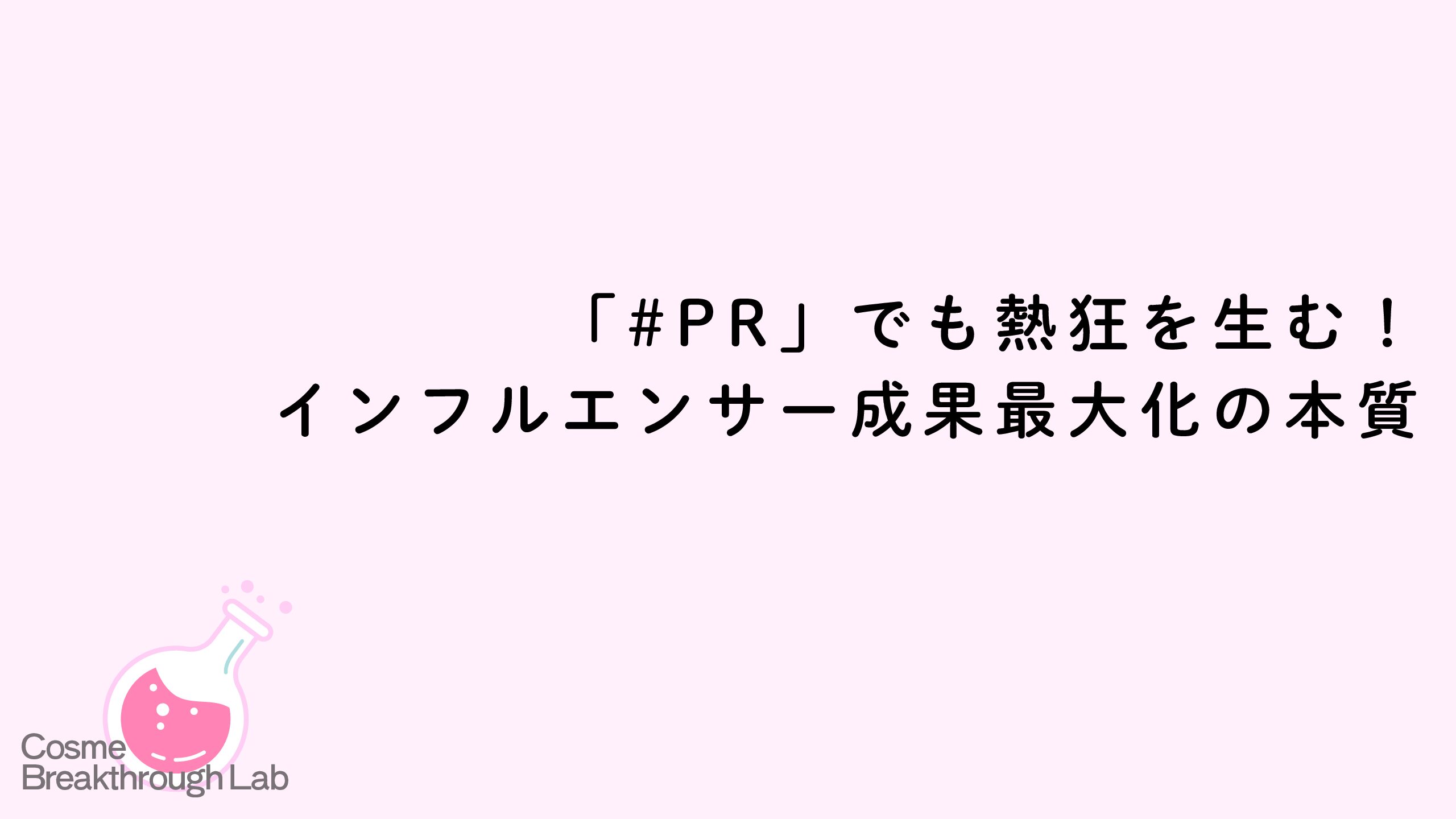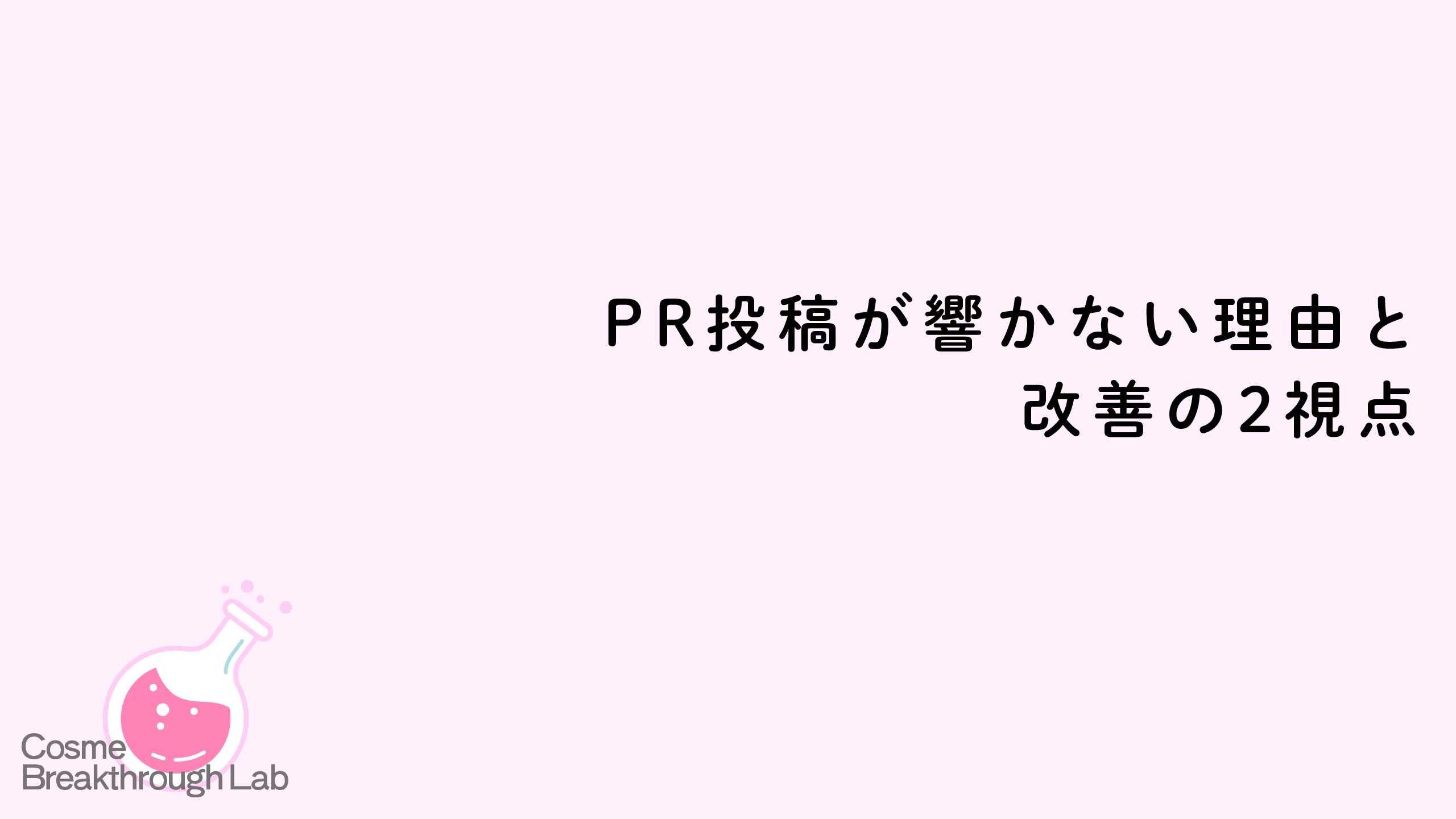「新商品の認知を広げたい」とインフルエンサーに商品を送り、SNSキャンペーンを実施した。しかし、集まるのは「商品をいただきました、ありがとうございます!」「使い心地が良いです」といった、当たり障りのない投稿ばかり。
もしあなたが今、そんな「お礼投稿の山」の前で立ち尽くしているのであれば、その原因は努力不足でも、商品の魅力不足でもありません。多くの企業が見落としている、施策の根本的な課題がそこにはあります。
それは、ユーザーに「戦ってもらう場所」を間違えている、ということです。
私たちも過去、素晴らしい商品と作り手の情熱がありながら、大手と同じ消耗戦に巻き込まれ、その価値を伝えきれずに苦しむ企業様を数多く見てきました。その経験から断言できるのは、戦い方を変えれば、資本力で劣っていても必ず突破口はある、という事実です。
UGCキャンペーンが失敗する2つの理由
なぜ、多くのUGC施策は「差別化なき消耗戦」となり、貴重なマーケティング予算を浪費するだけで終わってしまうのでしょうか。それは、多くの担当者が無意識に陥っている「思考のワナ」に原因があります。
理由1:「良いモノだから、良いと投稿されるはず」という期待
商品の品質に自信があるほど、私たちはユーザーにその「良さ」をそのまま伝えてほしいと願います。しかし、「良い」という感想はあまりに抽象的で、他の無数の「良い」という声の中に簡単に埋もれてしまいます。
これは、ユーザーに商品の「評価」を求める行為です。そこには、ユーザー自身の創造性を引き出すキッカケがありません。
理由2:「投稿数(KPI)を増やさなければ」という目的化
UGC施策のKPIを「投稿数」や「ハッシュタグの件数」に置いてしまうと、いつの間にか手段が目的化してしまいます。数を追いかけるあまり、インセンティブ頼りのキャンペーンになり、結果として熱量の低い投稿ばかりが増えてしまうのです。
これは果たして、本当に「認知が広がっている」状態でしょうか。もしかしたら、ただのノイズを増やしているだけかもしれません。
UGCを成功に導く2つの思考法
では、どうすればこの状況を打開できるのか。その鍵は、ユーザーを単なる「評価者」から「発明家」へと変えることにあります。
UGCの本質は「評価」をしてもらうことではありません。ユーザー自身に「発明」を楽しんでもらうことです。私たちの役割は「評価をお願いする」ことではなく「ユーザーが発明したくなる”遊び場”をデザインする」ことなのです。
この結論は、数々のブランド支援を通じて得た、成功と失敗の経験に裏打ちされています。
『Creatorスカウト』:特定のペルソナに影響力を持つインフルエンサーをデータに基づいて探し出し、直接アプローチすることで、無駄のない効果的な施策を実現します。
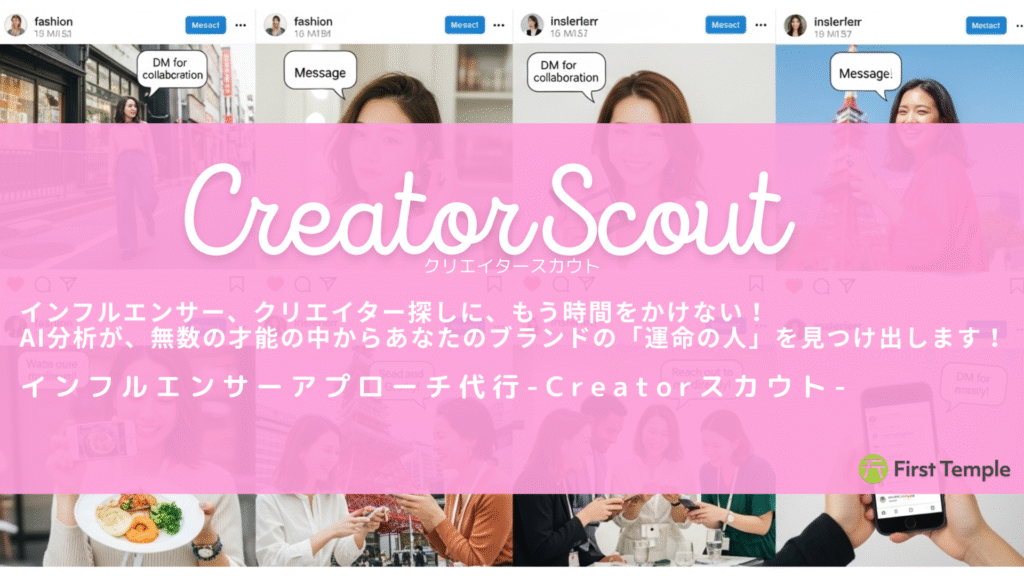
思考法1:ユーザーを「お客様」から「共犯者」へ再定義する
あるドラッグストアコスメブランドを3年で売上100億円規模に成長させた際、私たちは業界の常識を疑い、「本当の顧客は誰か?」を問い直しました。そして、棚の決定権を持つ「流通バイヤー」こそが最重要顧客だと再定義し、BtoB戦略を優先することで大きな成功を収めました。
この思考はUGCにも応用できます。UGCにおける「本当の顧客」とは、商品を”使う人”であると同時に、ブランドの魅力を”広める人”です。
彼らを単に「感想をくれるお客様」として見るのではなく、「ブランドの新しい魅力を一緒に発見してくれる共犯者」と捉え直すのです。そうすれば、企業からの一方的なお願いではなく、「この商品の新しい使い方、一緒に見つけませんか?」という、双方向の問いかけが生まれます。
思考法2:「正解」を提示せず「問い」を投げかける
あるD2Cヘアケアブランドの立ち上げでは、半年で約20万人の新規購入者を獲得しました。この時、私たちは業界の常識だった「悩みを煽る訴求」が、実は顧客が本当に求めているものではないと突き止めました。顧客の本音に耳を傾け、「ポジティブな未来」を提示する全く新しいコンセプトを打ち出した結果、市場から熱狂的に受け入れられたのです。
UGCも同様です。企業が「この商品の正しい使い方はこうです」と正解を提示してはいけません。「あなたなら、どう使う?」とユーザーの創造性を刺激する「問い」を投げかけるのです。
例えば、「このアイシャドウ、まぶた以外に使うとしたらどこ?」といった、あえて”正解”を外すような問いが、ユーザーの「自分だけの使い方を発見したい」という意欲を掻き立て、”発明”を引き出します。
明日からできる「発明」を促す仕掛けの作り方
思考の転換は、小さな行動から始まります。高額な予算は必要ありません。まずは、あなたのチームで、既存の資産を活用して新しいUGCの種を見つけることから始めてみましょう。
例えば、既存のお客様の声を元に、AIツールなどを活用して「もしこのお客様がYouTuberだったら、どんな『裏技』を紹介するだろう?」というテーマで、動画シナリオの草案を作成してみるのも面白い試みです。
ぜひ、あなたのチームで、以下の問いに対する答えを書き出してみてください。
- 私たちのユーザーを「共犯者」と捉えた時、一緒に解決したい「小さな不満」は何か?
- 商品の「公式の使い方」をあえて無視するなら、どんな「邪道な使い方」が考えられるか?
- 次のキャンペーンで「評価」ではなく「発明」を促すなら、どんな「問い」を投げかけるか?
あなたのブランドの熱い思いを、届けるべき人に届けるために
本記事でご紹介したのは、小手先のテクニックではなく、UGC施策の根底にあるべき「視点」の話です。
ありきたりな「お礼投稿」の山から抜け出す鍵は、ユーザーを「評価者」から「発明を楽しむ共犯者」へと、その役割を再定義することにあります。
作り手の「熱い思い」が込められた素晴らしい商品には、作り手自身も気づいていない無限の可能性があります。その可能性をユーザーと共に発見し、分かち合うプロセスこそが、本物のファンを育て、ブランドを強くするのです。
もし、あなたが一人でその「問い」を立てることに難しさを感じたり、思考を深めるための壁打ち相手が必要だと感じたなら、私たちはいつでもあなたのブランドの「かけこみ寺」として存在します。
▼UGC戦略の壁打ち、してみませんか?
この記事を読んで、自社のUGC戦略をもう一度深く見つめ直したいと感じたら。あるいは、ユーザーとの新しい関係性を築くための客観的な視点が必要だと感じたら。ぜひ一度、私たちの無料相談をご活用ください。私たちは、あなたのブランドの情熱を成功に導く、伴走パートナーです。